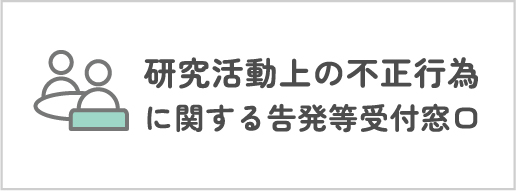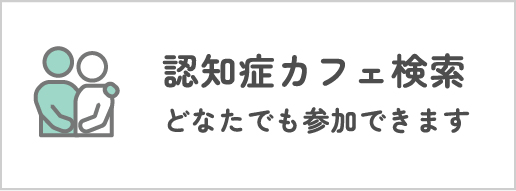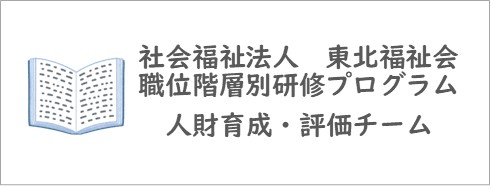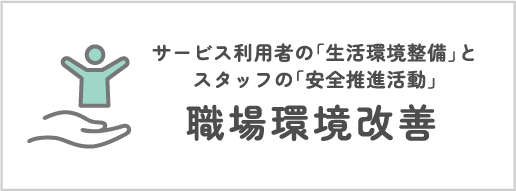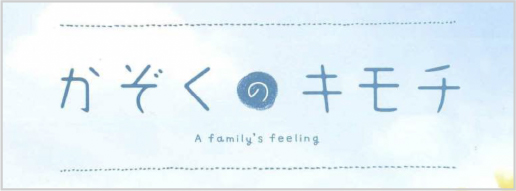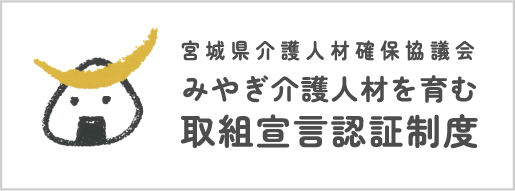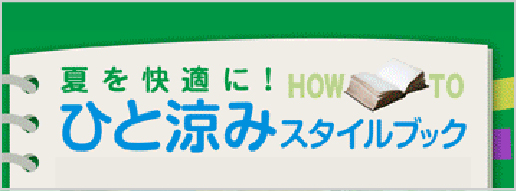リスクマネジメント指針
2012.03.15 Thursday 16:52
Ⅰ.施設における介護等事故の防止に関する基本的考え方
○ 基本方針
1)介護等サービスのご利用者がもっている心身にわたる生活上のリスク、ご利用者のご家族やその他の来訪者、スタッフにかかわるリスク(以下「生活リスク等」という。)を、無害化または軽減できるように努めます。
2)介護等の事故が発生した場合には、迅速かつ適切な対策を行うように努めます。
3)ご利用者の人権を尊重する意識の徹底をめざし、リスクマネジメントに関する体制の整備を行います。
4)リスクマネジメントの基本方針の内容は、管理者及びスタッフに周知、理解させます。
Ⅱ.介護等事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項
1.管理者の関与と責任の明確化
Ⅰ.リスクマネジメントの基本方針に沿って、リスクマネジメントに取り組む体制と責任を明確にします。
2.原因分析・課題抽出・仕組みづくり
1)リスクマネジメントに関する委員会などを設置して、生活リスク等の情報(以下「リスク情報」という)や対策の共有を図るとともに、事故予防対策のための仕組みをつくります。
2)リスク対策担当者及びリスクマネジメントリーダー、サブリーダーを配置して、その役割と権限を明確化します。
3.現場の創意工夫を活かす
サービス改善の提案やスタッフによるケアの工夫などをキャッチする仕組みを構築するとともに、スタッフ自らの創意工夫によってサービスの質を改善していこう、という意識の高揚を図ります。
4.リスク情報をキャッチしやすい環境づくり
スタッフがリスク情報を出しやすい環境づくりをして、リスク分析を行う組織を設置します。
1)事故や安全に関する情報収集
2)サービス改善のための情報分析
3)リスクマネジメント方針の策定
4)リスク対策の実践
5)リスク対策実践の検証
6)リスク対策の標準化
という、リスクマネジメントサイクルを循環できる組織づくりを行います。
5.生活リスク等に気づくこと
現在のサービスのなかに内包されているリスクに気づき、その内容を把握するための方法、技能の開発に努めます。
6.ヒューマンエラーへの対策
ヒューマンエラーは避けがたいものであることを前提に、ご利用者やスタッフ間のコミュニケーションを重視して、ヒューマンエラーの予防、軽減できるよう努めます。
Ⅲ.介護等事故の防止のためのスタッフ研修に関する基本方針
○ 研修・教育への取り組み
1)安全で安心なサービス提供を行うにあたって必要なスタッフの役割・機能を明確化します。
2)生活リスク等への気づきを高めるスタッフ教育を実施します。
3)事故発生時の対応に関するシミュレーション、新任研修や階層別研修など、リスクマネジメントに関する技能向上の研修などを実施します。
Ⅳ.施設内で発生した介護等事故、介護等事故には至らなかったが介護等事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ・はっと事例)及び現状を放置しておくと介護等事故に結びつく可能性が高いもの(以下「介護事故等」という)の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
1.事故報告書(アクシデント報告)
1)発生した事故は、所定様式による「事故報告書」を作成して、一元的に管理します。
2)報告内容は、事故の日時、場所、状況、事故後にとった処置、考えられる原因のほか、検討した再発防止策、ご利用者やご家族の反応なども記録します。
2.ヒヤリ・はっと事例(インシデント報告)
1)発生した事故だけではなく、ご利用者の損害に至らない「ヒヤリ」としたり、「はっと」した体験(ヒヤリ・はっと事例)をレポートとして報告して、分析することによりリスク対策を検討します。
2)レポート内容は、発生した場面など、事実の確認、原因の特定や分析、予防のために必要な情報を記録します。
3.記録作成上の留意点
1)個人情報の保護、記録の保管等のためのルールを別に定めます。
2)記録の様式は、定期的に点検・見直しを行って改善します。
4.事故要因の分析
事故報告書やヒヤリ・はっと報告書、ソフト面、ハード面、環境面、人的面などから要因分析を行って、再発防止のための方法などを策定します。
Ⅴ.介護等事故の予防や事後対応に関する基本方針
○ マニュアルの作成
1)リスク情報の共有、事故発生の対応、日常生活支援(ケア・サービス)に関するリスクマネジメントマニュアルの作成、ケアマニュアルにおける安全対策などを盛り込むようにします。
2)マニュアル等は、定期的に見直し・改善を行うようにします。
Ⅵ.ご利用者等によるこの指針の閲覧に関する基本方針
○ ご利用者等の理解に向けて
1)リスクマネジメント指針などをご利用者やご家族等が閲覧できるようにします。
2)ご本人がもつ要因によって起こりえるリスクについて説明するように努め、ご利用者やご家族等との信頼関係の構築を目指します。
Ⅶ.その他介護等事故の発生の防止推進のために必要な基本方針
1)生活リスク等の発見・把握のための「予防措置」を講じるよう努めます。
2)事故の要因分析と再発防止策の検討を積極的に行います。
3)苦情・相談対応体制を活用して、ご利用者やご家族等の声を、サービスの改善に活かしていきます。
(附 則)
この指針は、平成19年3月1日から施行する。