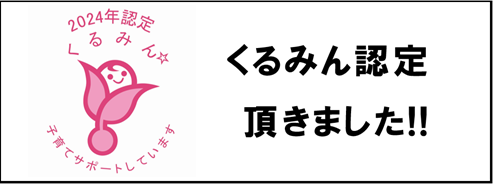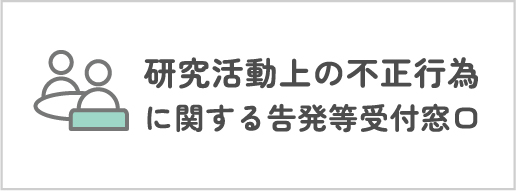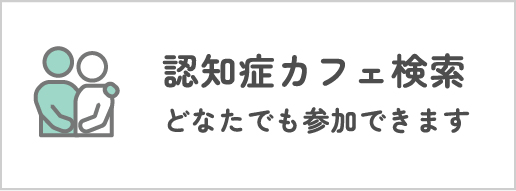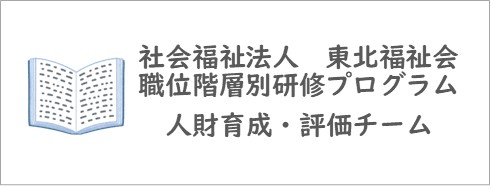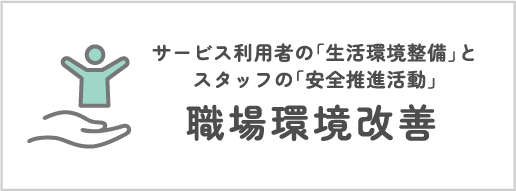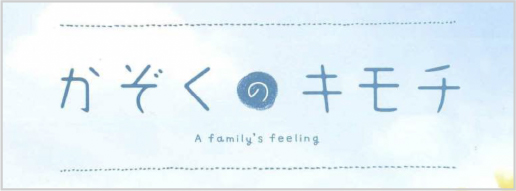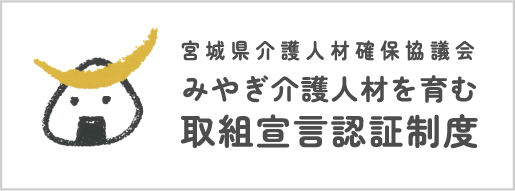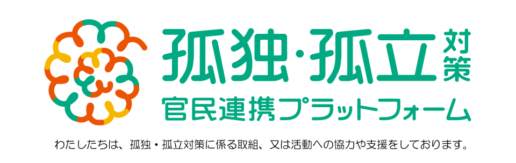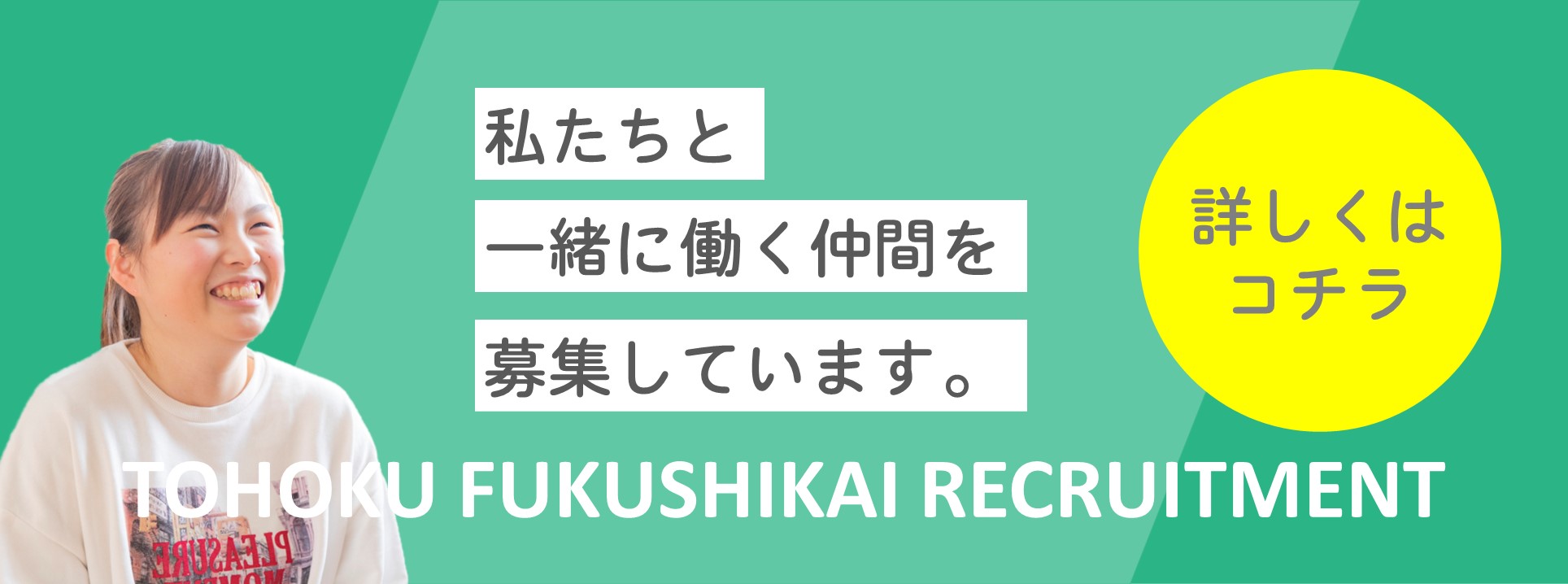新着情報TOPICS
法人本部 研修・実習
-
2023/09/06 法人本部
令和5年度:法人研修 職位階層別研修を開催しました
-
2023/04/27 法人本部
社会福祉法人 東北福祉会 職位階層別研修プログラム
-
2023/04/26 法人本部
令和5年度(法人)新任職員オンライン研修を開催しました!
-
2022/11/07 法人本部
令和4年度:新任職員フォローアップオンライン研修
-
2022/05/16 法人本部
【動画】2022(法人)新任職員オンライン研修を開催しました!
-
2022/05/11 法人本部
卓上カーリング☆実習生企画(せんだんの館)
-
2022/02/08 法人本部
FUKUSHI meets!!2023 に出展します!!
-
2021/11/05 法人本部
令和3年度 新任職員フォローアップオンライン研修を開催しました!
-
2021/09/21 法人本部
<求職者の皆様へ>東北福祉会を知って頂くためのWEB説明会を実施しています
-
2021/09/12 法人本部
令和4年4月1日付新規法人職員採用試験を実施致します。
-
2021/09/03 法人本部
令和3年度:新任職員オンライン研修
-
2020/12/28 法人本部
みんなの笑顔プロジェクト(実学臨床教育2年生企画)
-
2020/12/04 法人本部
医療用ガウンの正しい着脱方法・感染症対策を学びました
-
2020/11/27 法人本部
(社福)東北福祉会 WEB説明会開催しています
-
2020/11/14 法人本部
令和2年度 法人職員研修(オンラインver)を開催しました!
-
2019/12/25 法人本部
令和2年度 東北福祉会新規採用法人職員内定式を開催しました
-
2019/11/09 法人本部
2019年度 法人新任職員フォローアップ研修を開催しました!
-
2019/10/29 法人本部
(報告)認知症サポーター″ステップアップ″講座&寄り添いボランティアのすすめ
-
2019/10/16 法人本部
石巻地区介護・福祉フェスティバルが開催されます!!
-
2019/07/31 法人本部
無料公開講座「介護×ICT 変えようケアワーク」介護ロボット等機器に「触れて体感」「使って実感」セミナー参加者募集中!