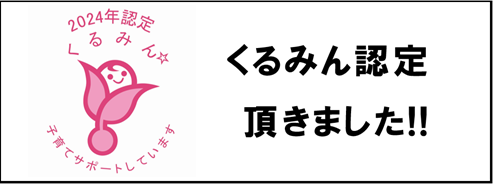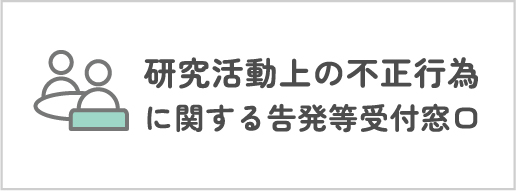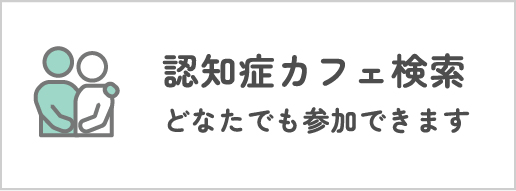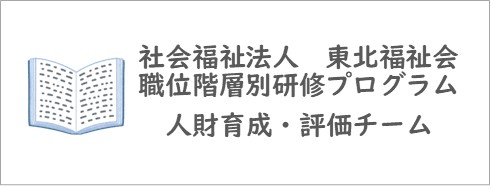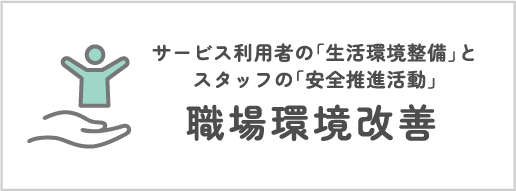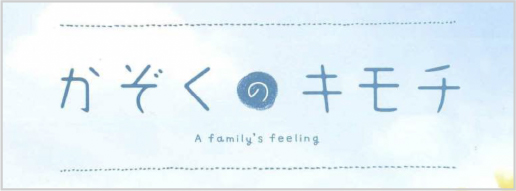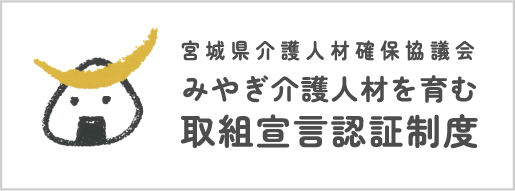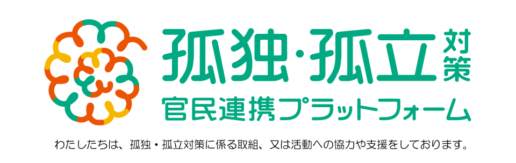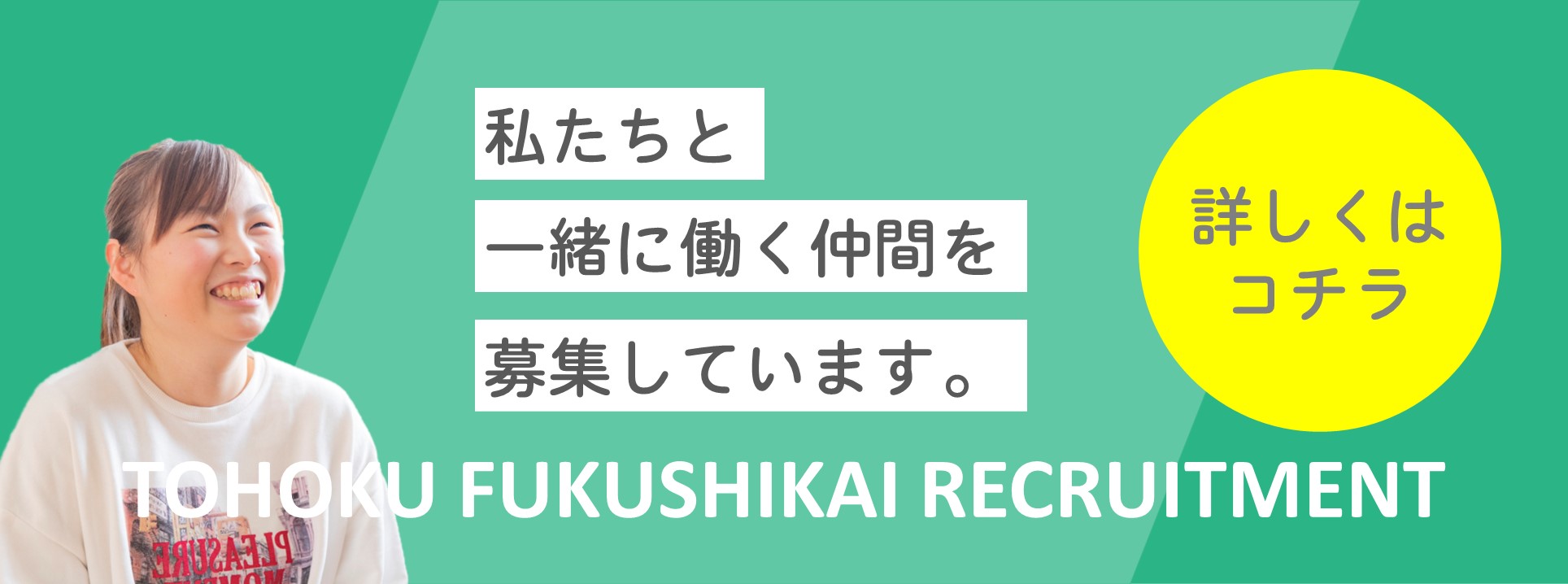せんだんの杜SENDANnoMORI
せんだんの杜 これから出会う皆様へ(せんだんの杜ブログ別版)
-
2021/07/27 せんだんの杜
care for careworker プロジェクト実行委員会様より頂戴しました
-
2020/03/05 せんだんの杜
せんだんの杜 放課後等デイサービス事業の自己評価・保護者評価の公表について
-
2015/07/29 せんだんの杜
これから出会う皆様へ:No5
-
2015/06/23 せんだんの杜
これから出会う皆様へ:No4
-
2015/04/08 せんだんの杜
これから出会う皆様へ:No3
-
2015/03/12 せんだんの杜
これから出会う皆様へ:No2
-
2015/03/05 せんだんの杜
これから出会う皆様へ:No1